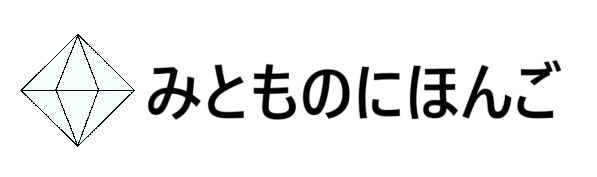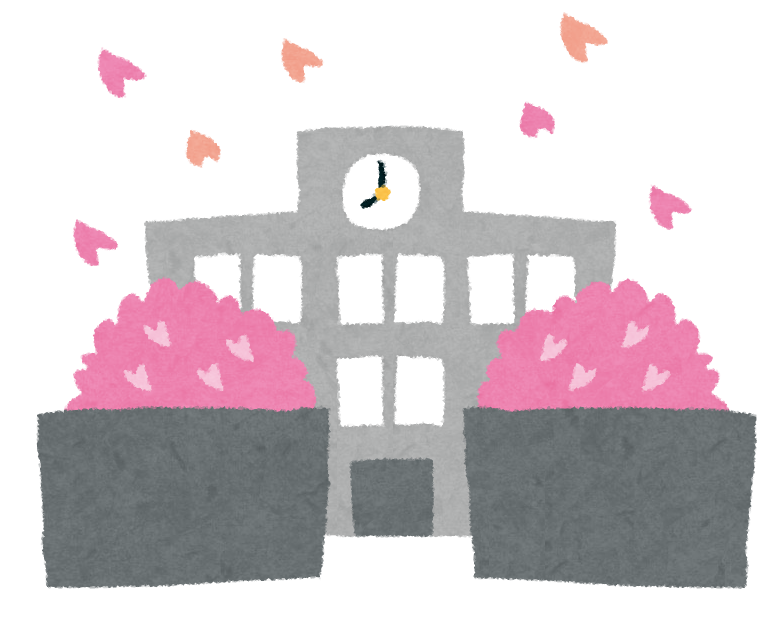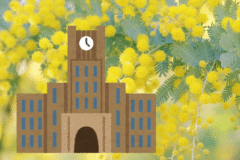こんにちは、Mitomoです。
先日、令和6年度 日本語教育能力検定試験の結果が発表されました。

独学で初めての受験でしたが
運よく一発合格できました!
この記事では、独学で合格した学習法を紹介します。
あくまで私の場合ですが、参考程度にお付き合いいただけますと幸いです。
2024年1月 受験を決意
私が日本語教育に興味を持ち始めたのは、2023年の初冬。
新たに国家資格となる「登録日本語教員」が話題になっていましたが、“試験の概要は2024年4月にならないと分からないことが分かった”という、もどかしい時期でした。
情報を集めるうち、“日本語教育能力検定試験の勉強をすれば日本語教員試験にも対応できそう”という口コミを発見!そして2024年の正月、「日本語教育能力検定試験」「日本語教員試験」のW受験を1年の目標に決めました。
“赤本”を購入
勉強するにあたってまず購入したのが、赤本と呼ばれる参考書。
『日本語教育能力検定 完全攻略ガイド第5版』です。
初めて実物を見たときには分厚さに尻込みしましたが、これが無くては始まりません。冒頭には試験概要と出題範囲の概要がまとめられており、試験の全体像を掴むのにも役立ちました。
私はこの赤本を試験当日までに3回通読することになります。
とりあえず1度、読んでみた
知識ゼロからの学習、まずは赤本を一通り読んでみることに。
概要を掴むために流し読みしていると、所々に日本史や現代社会の教科書で見た言葉が出てくるんです!これらを見つけたときには少し嬉しい気持ちになりました。
読む順番を工夫
赤本通読1周目、私は第5部の「社会・文化・地域」から始めました。なぜなら学生時代に社会や地域コミュニティについて学んでいて、一番興味があったからです。
いきなり言語教育の専門用語ばかりでは難しくて挫折する気がしました。
自分のやる気をコントロールするのも独学のポイントです。
赤本1周目はこの順番
- 第5部 社会・文化・地域
- 第4部 言語と社会
- 第3部 言語と心理
- 第2部 言語と教育
- 第1部 言語一般
- 第6部 音声分野
- 第7部 記述問題
赤本2周目
赤本の通読2周目は、前(第1部)から順番に。流し読みだった1周目と違い、ノートを取りながらじっくり読み進めました。
メモノートは雑でいい
ノートには赤本を読んで重要だと思った用語や、つながりがある内容をまとめる形でメモしていきました。あくまで脳内を整理するために、文字の丁寧さにこだわらず雑多に書いた感じです。
試験問題は脇に置いて
試験勉強において“どう出題されるか”という視点は大事ですが、基礎知識もない段階ではどうしようもありません。最初は過去問に手を出さず、赤本に集中しました。同じ理由で「記述問題」も後回しにしました。
赤本3周目
3周目は、2周目のメモノートを見ながら進めました。
2周目の時に自分がメモした部分を見直しつつ、改めて大事だと思ったことを違う色のペンで追記していきます。
そして特に暗記が必要と思った部分は、新たにまとめノートを作りました。
まとめノート
まとめノートに書いたのは試験直前に見返したい暗記事項です。
言語一般の品詞や敬語の区分、外国語教授法や調音点・調音法など、赤本に記載されている表を参考に自分が見やすいようアレンジして清書しました。
ノートにまとめた知識区分
- 第1部 言語一般
- 第2部 言語と教育
- 第6部 音声分野
ここで作成したノートはこのあと過去問を解く際にもかなり役立ったので、赤本を読みながら作っておくことをおすすめします!
問題集を解く
赤本3周目と並行して、問題集に取り掛かりました。
『日本語教育能力検定試験 合格するための問題集』です。
問題集を解く一番の目的は、試験の出題スタイルを知ること。分からない問題は「まとめノート」を見ながら回答し、答え合わせ後は問題集の解説と赤本を見比べて知識を確認していきました。
過去問に挑戦
過去問は令和3年・4年・5年度の直近3年分を解きました。
回数は、各年度3回ずつくらいです。
もっとたくさん解いたという方も見かけたのですが、私が3年分にしたのは、日本語教育を取り巻く状況が変化する中で問題のトレンドも変わっているだろうと考えたことと、一冊の値段が安くないことが理由です。
過去問はこう解きました
- 問題を制限時間内に解く
- 答え合わせ(正答率を出す)
- 解説と赤本で確認(正解した問題も)
- まとめノートに追記
正答数と正答率を記録しておくと、解くたびに自分の成長が分かってやる気が出ました。全問正解ということはなかったですが・・・。
正解した問題の解説もしっかり読み、理解が甘いところをまとめノートに追記しました。取り組む回数が少ない分、1回1回を濃い内容にして徐々に正答率を上げられるよう心がけました。
用語集を活用
過去問には赤本で詳しく説明されていない用語も出題されます。
そこで『改訂版 日本語教育能力検定試験に合格するための用語集』も購入して、過去問に出てきた用語を確認していました。
赤本内に記載されている言葉も、用語集の説明文と読み比べることで知識が深まります。その内容も「まとめノート」に追記して、知識を整理していきました。
記述問題の攻略法
記述問題に取り掛かったのは、試験1か月前くらい(9月ごろ)でした。
赤本と問題集に加え、記述に特化した参考書も使用しました。
『改訂版 日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題40』です。
独学は添削してくれる人がいないのが辛いですが、まとまりのある内容に仕上げるには何度か書いて慣れる必要があると感じました。
記述問題の対策
- 赤本 「第7部 記述問題」を読む
- 『合格するための問題集』の記述式の解説を読む
- 『合格するための記述式問題40』「講義編」で基本を理解
- 『合格するための記述式問題40』の例題を解く
“よくない解答”を反面教師に
独学でもできる対策は、減点されない文章にすることです。
『合格するための記述式問題40』では例題に対する“よくない解答例”が示され、それがなぜよくないのか分かりやすく解説されています。
例題を解いたら自分の文章で“よくない例”に当てはまっている部分を徹底的に修正しました。すると自分の書き方の癖が分かり、本番で気を付けるべきことも明確になりました。
正しい答えを探さない
記述問題では実際の教育現場を前提に「あなたならどうするか」と問われることがあります。しかし受験生の多くは指導経験が無く、また最適な対処法はその時々で変わるものでしょう。
問われているのは意見の正しさではなく、いかに説得力のある主張ができるかという点。これは忘れないようにしていました。
10月27日 試験当日
長々と書いてきましたが、ついに試験当日です。



慣れない早起きもがんばりました
この日、私のリュックの中には「まとめノート」が3冊。これが試験のお守りでした。
試験会場の席についてソワソワした気持ちに襲われたとき、自分の字で書かれた表を見ながら気持ちを落ち着けました。あとはこれまでの努力を信じて試験に向き合うだけです。
12月20日 合格発表
試験の感想は「全く分からなくもなかったけど、手ごたえもない」でした。特に記述は一度書き直したため時間ギリギリになり、あわてて書いた「日本語」は「にほんご」と平仮名になる始末。それでも望みは捨てません。
インターネットで結果を確認すると「合格」。
ほっとしました。おかげでこの記事を書けています。
“一発合格!”と先に書きましたが、もし不合格でもまた受験したと思います。なぜなら、勉強して「日本語教育っておもしろい」と実感したからです。
まだスタートしたばかり、これからも日本語教育について学んでいきます。



つたない体験記ですが
どなたかの参考になれば幸いです
ちなみに日本語教員試験は残念ながら不合格でした
また別の機会にレポートします!